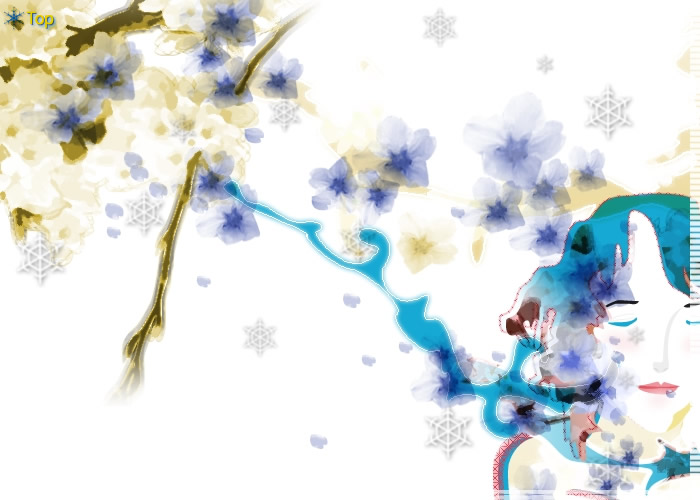
Christmas Eve
歳の瀬もあと一週間ほどという或る日、0時過ぎに彼から電話が鳴った。
「今何してる?」
「特になんにも。なんだか眠れなくって。」
「これから山の方へドライブに行かないか?君にどうしても見せたいものがあるんだ。」
「ん・・・いいわ。でも三十分待って。」
「OK、迎えに行く。それから、毛布を一枚用意しておいてくれ。」
「毛布?わかったわ。じゃ、後でね。」
彼は私と同じ大学で二階下の研究室にいる先輩だった。付き合うようになって三年は経っていたが、昼間は学生、夜や休日は働いている彼とどこかに出掛ける機会はあまり作れなかった。たまたま日曜日に彼の仕事が入っていないと、晴れていればお弁当を持って、近くのスキー場までのドライブをねだった。
車で三十分余り、シーズンオフのこのスキー場が私は大好きだった。夏になると県外からもラグビー部連中の合宿で暫くの間は活気づくが、広大なゲレンデを持たないこのスキー場を知り利用しているのは、殆どが地元の人間だった。
クローバーやタンポポやレンゲが咲いた緑の丘にシートを敷き、お弁当を広げ、高原というよりはいくつもの峰々を背に、彼にくっつき腕を組みながら食べる。人影は疎らだから、恥ずかしいことはなかった。例え人がいたところで、彼とひっついていることに変わりはなかったろう。
梅漬けを入れたおにぎりを食べた後は、残った種を決まって彼はぴゅううと草の上に飛ばした。「そんな風に捨てちゃだめ」と云うと「種は土に帰すものなんだよ」と云う。そんな言葉を話す唇にすかさず私はキスをした。
たこウィンナーとか兎リンゴを「俺は子供じゃないんだぞ」と云いながらも嬉しそうな顔をして食べてくれた。母親ゆずりの甘い卵焼きを「とても美味しい」と云ってくれた。その度にわたしは彼の唇にキスをした。
飲み物は途中のコンビニでペットボトルの烏龍茶を買って来て回し飲みした。粗方お腹いっぱいになると、彼は私をゆっくり抱きしめて、両手で優しく頬を抱えて長いキスをした。それが"ごちそうさま"の挨拶だった。それから私の膝を枕に目を閉じて横になる。そのうとうととする少し窶れた横顔を見つめて髪を撫でながら、私はいつも彼と一緒に高原の風の中にいた。
二人のまわりでゆったりと風が吹き抜けている。ハコベやペンペングサがそよそよと揺れている。彼と来られるここは時間がゆっくりとうとうと流れる唯一の場所だった。
私は彼が大好きだった。
急いで外に出られる服に着替え、髪を梳かしながら、暖かいココアを作る。ミルクに粉末カカオを溶かして作る本格的なホットチョコレートが彼の好物だからだ。
はじめて彼が私の部屋に訪ねてきたのは、音もなく雪が降りしきる真冬の真夜中だった。私は高分子材料学レポートを書き上げてココアを作っていた時だった。
ドアのノックの音と「遅くにごめん。明かりがついていたから。」と静かな彼の声が聞こえた。先輩がこんな時間にどうしたんだろうと、おそるおそるドアを開けると、「遅くにごめんな、仕事の帰りなんだ。これ渡したくて。誕生日おめでとう。」と体半分だけ開いたドアの隙間から茶色の箱を差し出した。
思いがけない来訪と突然のプレゼントに戸惑い、きちんとお礼も云わぬまま開けた箱には、私の大好きなお菓子屋さんの紅玉ジャムの瓶が入っていた。シナモンと甘酸っぱい林檎の香りが、彼と私を包み込む。
すぐに帰ろうとする彼を引き留めたのは私だった。「今ココア作ってたんです。召し上がっていきませんか。」
彼は私の部屋にちょこんと所在なさげにストーブの前に座っていた。コートも着たままだった。
「砂糖はどうしますか?」と聞くと、彼は暫く私の顔を見つめた後、満面の笑みで目を細めてこう答えた。「そうか、君も砂糖は入れないだね。実は僕ね、ココアが大好きなんだ。喫茶店で飲むこともあるけど砂糖なしにはなかなかお目にかかれないから・・・」
彼のコートを脱がせたのは私だった。二人で暖かくてほろ苦いココアを飲んだその時から、私は彼がたまらなく好きになったのだ。そして私達はその日から恋人同士になった。
出来上がったココアを携帯用ポットにいれ、毛布を用意し、口紅を引き終わった頃に彼の車のエンジン音が聞こえてきた。
それを合図に部屋の明かりを消し、ドアに鍵をかけ、彼のもとへ急ぐ。
荷物を抱えてマンションの階段を降りてきた私を見て、彼は車のドアを開けてくれる。いつもの彼だ。
「さあて、出発!」
到着した場所はいつものスキー場よりもう少し山の上だった。山道に沿って車が10台くらい停まれるほどのちょっとした広場だった。
「外に出て、上を見てごらん。」
彼に云われるがまま寒空の下に出て空を見上げると、そこは降るような星の下だった。
「今日は新月って知ったから、晴れていたし、きっと星が見られると思ってね。」
「すごいすごい」「こんなのはじめてよ・・・」
二人で体を寄せ合い一つの毛布に包まって星を眺め続けた。あんなに存在感のあるカシオペアやオリオンが数多ある星の一部だった。天の河も見えた。星空は漆黒の湖に煌く魚の鱗だった。
暖かいココアをすすりながら、いつまでもいつまでも眺めた。やはり時間はゆっくりと流れていて、首の痛さもお尻の冷たさもさほど気にならなかった。
「流れ星、降らないかなあ。」
「どうかな?魚みたいに口開けてると見ることが出来るって聞いたことあるよ。」
「あはは、ほんとかなあ。この際なんでもいいや。やってやるぞーパカンパカン」
馬鹿みたいにパクパクしている私の口の中に、まん丸の何かが転がってきたのは、そのすぐ後だった。驚いて目をまん丸にしている私だったが、その何かが甘露飴だとすぐ気付く。
「星を飲み込んじゃうのかと思ったよう。んもう、息が止まりそうだよう。」
「あはは、ごめんごめん。」いたずらっぽく笑いながら、彼も自分の口に飴玉を放り込んでいた。
「だーめ、許さないんだから。」そう云って私は唇で彼の唇を塞ぐ。
なんだか甘い甘い蜜のいっぱい入った林檎のような味がした。彼と私と星の湖が全世界だった。時間が止まる魔法にかかったとしたらこんな感覚なんだろう。
ココアを飲んでキスをして星をみてキスをしてココアを飲んでキスをして星をみてキスをして、唇が離れる度、―ロマンティックをとめて―、と願った。何度も何度も繰り返した後、辺りの草木が目を覚ます頃には、飴玉みたいにとろけてしまった私を彼が抱えて車に乗せてくれた。
彼は私を部屋まで送った後の帰り道、本当の流れ星になって、夜空へと消えてしまった。
あれから何年も経ち私は星の数ほどの涙を流し、幾つか恋もした。
私の記憶の中には、若かった私と彼のあの頃の想い出は消えることなく、空の星の如くゆったりと瞬いている。
いつまでも、きっといつまでも。
©Copyright 2001 soupooh(WOGUCHI,Tohco)