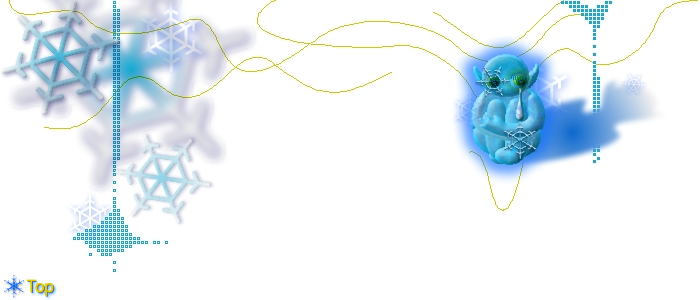
ココンカタルシス
思い出は時間を経ると共にろ過されて、きらきらと足元に堆積している。私は無邪気に微笑んでいる。「それでも、やっぱり楽しかったよ」と、サラサラと風化されるままにまかせている。
不可思議なメールが届いていたのだった。
決して痛くはないが胸の奥の内側がざらざらする。何年か振りの見覚えのある名前。たった一言が、いかにもあの人らしい、気がする。
あやふやなのは不思議に思うかもしれないけれど、どうしても私はあの人の本当の名前が思い出せないからだ。あの頃の記憶が欠落してしまっているのだった。四年前の冬の間ぼんやりと彼と過ごしたことはわかっているけれど、鮮明に覚えているのはクリスマスイブの震えた夜だけだ。後は痛哭感情だけしか蘇ってこない。ただかなしいだけかなしいだけ。
だからこのメールが彼のものであるのか、本当は私はよくわからない。
―たしか、楽しかったはずだけれども―
―いっぱい愛し合ったはずなのだけれども―
記憶の中から、あの人に惑溺し眩惑させられた日々を探し出すことができない。探し出そうとすればするほど、足元はギラギラと光り輝き頭の中でハレーションを起こす。
ふらふらと眩暈を起こした私が、忘却の彼方を彷徨いながら思い出すことは、むかしむかし或る冬の夜に起こったあの出来事だけなのだった。
引っ越したままのダンボールに囲まれて、独りでベットに座っている私。
オンラインのパソコンを前にして、震える声で問い掛けたただ一つの本当を、肯定も否定もしなかったあの人のぼんやりした輪郭。
二人で居ても孤独という絶望。
体じゅうが震えちゃって、どうしようもなかったのだった。気が付くと嗚咽も内臓も全部ぐちゃぐちゃと放り出すようないきおいで、水洗が渦巻く便器の中へ頭を突っ込んでいる。
むかしむかし或るところにいた私。
声なんて思い出せない。名前だって顔だってもう、なにもかもよく思い出せないのに、最後の夜のあのラストシーンだけを、鮮烈に思い出してしまうの。
それだけなの。
忘れたいのに。
忘れたいけど。
忘れられなくたって。
叶わないこととはわかっている。
それでも私は微笑んでいる。今、此処に居る、私。
©Copyright 2001 soupooh(WOGUCHI,Tohco)