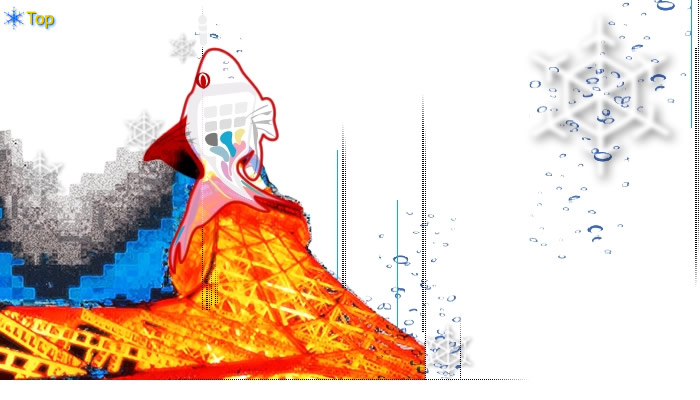
行く宛てのない河
洗面所のドアがパタンと閉じられた。暫くしてシャワーの音がする。
わたしには河が流れ出したように聴こえた。ゆく宛てもなく河が流れていく。
「どうしてそんなことをいうのですか?
あなたをすき、それだけはなにもかわっていないのですよ。」
「わかっています、僕も君をすきなきもちはなにもかわっていないのです。
ただ、僕にはこれからのことがわからなくなってしまったのです。
でていってくれてもかまわないのです。」
「これからがどうなるのかなんて、わたしにもわかりません。
そこまできてしまったのですね。」
恋人同士ならば、あなたのせいよと諦めたり、誰のせいでもないと奇麗ごとを並べ立てて、それなりに別れの理由を羅列することができたろうに。
結婚しているものの別離とは、何故にこんなにも曖昧なのだろう。長い間には何度もぶつかり合い、その度に自問自答し、それでも互いに尊び合える人だと感じるからこそ、永遠に同化できない他人と暮らしていけることはわかっていた。自然に体に染み付く習慣のようにわかっていた。あなたがハムエッグを食べる時にはマヨネーズを使うとか、髭を剃る時は電気シェーバーではなく剃刀をつかうこととか、そういう諸諸の生活の一部として、ごく自然にわかっていたはずなんだけれども。
疲れて果てていた。わたしもあなたも。疲れたわたしはわたしに関わるすべて何もかもが億劫になっていた。あなたがそんなわたしを必要としなくなるのは当たり前なのかもしれない。
降るような河の音を聴きながら、鞄に身の周りの物をつめこむ。さして大きくもないボストンバックに、二、三組の下着、少しの化粧品、財布、それだけ入れた。替えの服や好きな本など詰め込むスペースなんてなかった。
最後に出掛ける前のいつもの癖で、香水を一吹きする。手に持ったのはYSLのシャンパーニュ。何故かこの香水を選んでいた。わたしには成熟し過ぎて似合わない香りなのに。しかもこんな時に。ばかみたい。
シャワーを浴びているあなたに一言声をかけたが、聞こえないようだった。
クリスマスも近い冬の夜更けはかなり寒かったが、鞄を抱えセーター一枚でふらふらと家のドアを開ける。
わたしは音に誘われるように巣箱から飛び出していた。
常識のある世間体、築き上げた社会的立場、約束された不自由の無い生活、そういうプライドなんてどうでもよかった。無くなってしまってもかまわなかった。
そしてその後に、リスクと呼ばれるどんな黒い河が待ち構えていることを考えてみても、どうにかなってしまうのかなんてわからなかった。今よりもマシなわたしになれれさえすれば、それでよかった。
ふらふらとゆらゆらと歩む姿に影ができるほど、妙に明るい月がわたしを照らしていた。そうか、わたしはまだ存在確認されているんだな。
大通りまで歩き、自分で肩をさすりながらしゃがみ込んでいるうちに、タクシーを飛ばしてきた男に拾われた。
乗り込む時にあの似合わない芳醇で耽美な香りの泡がはじけた。この香りを選んだ理由はそういうことかもしれない。と、またばかみたいなことを思う。
柔らかいシートに体を預け、タクシーは深夜の環状八号線を滑るように走っていく。流れに呑まれるように、渦に捲かれるように。沈み込んでしまうわたしを繋ぎとめているのは、覚悟を決めたという少しの自尊心と、月明かりと、顔のない男のなま暖かい手だった。
目の前の見知らぬ河の、いったい何処まで辿り着けるのだろう。
わたしを乗せたタクシーは、前へ前へと黒い闇に吸い込まれて行く。
©Copyright 2001 soupooh(WOGUCHI,Tohco)